① WEBマーケティングとは
① Webマーケティングはマーケティング全体の一部分

無理に売り込むのではなく、顧客に「買いたいので、どうか売って欲しい!」そう言わせるための施策です。
経営戦略の専門家ピーター・ドラッカーはこう言っています。
「マーケティングとイノベーション以外は全部コスト」 と。
つまりどういう事かというと、私の解釈はこうです。
「商品を作り(イノベーション)集客して販売する(マーケティング)これが全てだ」
広い意味でのマーケティングは、販売活動全般のことです。
これがインターネットの普及により、広くデジタル化したことによってデジタルマーケティングが普及しました。
- AI→人工知能
- AR→拡張現実
- VR→仮想現実
- IOT→家電製品・車・建物など、さまざまな「モノ」をインターネットと繋ぐ技術です。
などなど・・・これを使って集客して販売するのは個人ではちょっと難しそう・・・
もっと、イチ個人がフレキシブル(柔軟)に使えるデジタルのマーケティングはないかと考えた時に、あるのが「WEBマーケティング」です。

オウンドメディア(ブログやサイト)を使ったコンテンツマーケティングや、 Twitter や Instagram を使った SNS マーケティング。
ビジュアルに訴えかける YouTube などの動画を使ったマーケティングなど・・・
個人でも、もちろん企業でも今はフレキシブルに使える施策がたくさんあります。
コロナの影響も相まって一般の企業の間でも DX化がものすごい勢いで進んできています。

引用元:経済産業省 DX 推進ガイドラインhttps://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf
② Web マーケティングをもっと詳しく解説
私たちが自分の商品をもってネットで販売して行く時に行う Web マーケティング。
もっと具体的に身近な例に例えて解説していきます。
ブロガー

例えばブロガーなんかは、はっきりいってプロのマーケターです。
Webマーケティングの全体的なスキルをカバーしています。
集客して→価値を提供して→ファンになってもらって→行動してもらう(アフィリエイト広告とか)
この一連の流れを自分一人でやるわけです。
YouTuber

YouTuber なんかもそうですよね。
Webマーケティングの中でも、特にブランディングやファン化することに強みがあります。
顧客の興味のありそうなコンテンツ(動画)をアップして人を集めて、ファン化させ、なにかしらのマネタイズをする。
一般的にYouTuberのマネタイズ方法は、広告収益が多いと思いますが、ファン化させる力の強い YouTube ではマネタイズ方法はいくらでもあります。
それこそ、自分の商品を作って販売するのにはうってつけです。
WEB広告

広告もマーケティングでは切っても切れない方法のひとつです。
主に “集客” の役割を担います。
自分のターゲット顧客になり得るユーザーへ狙いを定めて広告を出稿すれば、自分の商品にベストマッチのユーザーを集めることができます。
また企業としては、販促活動の一環としてアフィリエイト広告を出稿し、アフィリエイターに拡散してもらって商品の PR をするマーケティング活動も一般的になってきましたね。
③ Webマーケティングのメリットとデメリット
Webマーケティングは個人で身につけるべき最強のスキルです。
言い過ぎではなくマーケティングスキルが身に付くと、どんなものでも販売することができるようになり、ビジネスの仕組み化・売上の自動化が可能になります。
メリット





デメリット


④ マーケティングに最適解はない
Webに限らずマーケティングには様々な組み合わせがあります。
目的によってその組み合わせは無限にあり、“たった一つの最適解” などはありません。
例えばーーーーーーーーーーーー
例えば、既に持っているサービスで実店舗のマッサージ店を運営していたとしましょう。
実店舗型だと地域に根付いているわけなので、地域名キーワードで SEO 集客をするのが有効かもしれません。
もしくは資金力があるなら、お金をかけてリスティング広告で集客するのもありです。
SEO 集客をするのであれば着地点であるオウンドメディア(ブログ)で、価値のあるコンテンツを提供する必要があるでしょう 。
※こういうのをコンテンツマーケティングと言います 。
もし個人色をバリバリ出して行きたいのであれば、 YouTube でブランディングをするのもありです。
視聴者をファン化させることができれば、地域外からお客さんが来ることもありえます。
はたまた、全く情報発信媒体を持たずに、広告からメルマガなどに誘導しナーチャリング(教育コンテンツで価値観を理解してもらう)し、LP(販売ページ)でセールスする流れもあります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 販売したい商品
- かけられるコスト
- 目標達成までの期間
これらによって幾通りもの方法をカスタマイズすることができます。
そして「どれが一番効果が出るのか?」は、やってみなければ分かりません。
実際にやってみてボトルネック(問題点)を見つけては改善し、ABテストを繰り返す。
これによって自分だけの最適解が見つかる、それが Web マーケティングです。
② マーケティング力は資産
そこでは、マーケティング力は資産というお話をしていきます。
資産と収入の違いについて理解があるでしょうか?
① 資産と収入

「昔はお金持ちだったんだよね・・・」という人はいても、「昔は資産家だったんだよね」という人はいません。
資産は一度築いてしまえばなくなることがありません。
資産というのはストック性のある価値の事を言いますから、資産が資産を生み出すんですね。
- 株や投資信託などの金融資産
- スキルや知識などの知的資産
このように有形資産と無形資産に分けられますが、Webマーケティングは無形資産の方に分類されます。
実働型の単発スキルではなく、資産性の高い総合スキルですから、一度身に着けてしまえばビジネスモデルを変えても何度でも再現することができます。
・誰に向けて
・どんなメッセージを届けて
・どうやって販売すればいいのか
この辺りのポイントを押さえていれば、 売る商品が変わっても売り上げは立つということです。
② Webマーケターは経営者
Webマーケティングは全体把握が求められるので、役割としては経営者寄りになります。
とはいえ、やることがたくさんあり、実務的なものから経営的なものまで様々です。

このように総合的なスキルであることから Web マーケティングは資産性の高いビジネスオーナーや投資家的な働き方に位置します。

③この講座のざっくりした流れ
ここでは、この講座のざっくりとした流れをお伝えしていきます。
目的や自身の事情によってやり方のパターンもかなりたくさんあり、その全てのパターンをこの講座でお伝えするのは現実的ではありません。
また、あまりにもやることが多岐に渡りすぎてしまい、迷ってしまうといけません。
ですから、最もオーソドックスかつ汎用性のあるマーケティングの流れを軸とし、この講座で指導して参ります。
現在、私自身が行なっているマーケティングは、態度変容モデルをベースにプロダクト(商品)から考えるWebマーケティングの方法です。




④自分に商品が作れるのか不安なあなたへ
ここでは、自分に商品が作れるのか不安なあなたへビジネスの基礎的な考え方をお話ししていきます。
「私に商品を提供できる強みなんてありません・・・」
こんなふうに答える人、めちゃくちゃ多いです。
非常に真面目で素晴らしいと思いますが、ビジネスとしてはちょっと考え方が違います。
誰でも変わらず、人と違った価値があります。
それは、ある人にとっては “喉から手が出るほど欲しいもの” の場合もあるんですね。
① 誰にでも強みがある
まずはっきりと言いますが、誰にでも “強み” というのはあります。
今までしてきた成功体験や失敗体験、自分の性格やコンプレックスなどは実はすべてあなたの強みになります。

これらが何もない人なんていません。
どうしても “自分の強み” と聞くと「誰かに語れるほど優れたことでなくてはいけない 」と思ってしまいがちです。
ですが、実はマーケティングする上で最も重要なのは “共感” だったりします。
失敗経験やコンプレックスなどのネガティブな情報も、 同じ悩みを抱えている人からしてみれば貴重な価値。
もちろん、自分が圧倒的に知識のあることだったり、実績のあること、成功したことなんかは権威性がありますから、話にも信憑性が生まれその内容にも価値が生まれます。

どちらもあなたの強みになりますよ!
② 今から強みを見つけるパターン
それでもどうしても自分の強みが見つからなかったり、上がった項目の中でビジネスに結びつかないのであれば、今からビジネスに繋がるような強みを見つけるパターンもあります。

まず、これからビジネスにつながる強みを見つけるためには、圧倒的にその分野について勉強しなくてはいけません。 勉強するにしても、ビジネスにつなげるためには三日三晩で知識の蓄積はできませんよね?
そこでポイントになってくるのが、 「情熱を持って勉強できるのか?」というところです。
ただ「お金になるから」のような理由で、圧倒的な学習は継続できません。
自分がそもそも挑戦したいと思っている分野だったり、興味がある分野でなくては、成功するために最も必要な “継続” が困難になります。
もちろん情熱が持てる分野だったとしても、逆にお金にならない市場であった場合、それはビジネスには結びつきません。


この辺りの整合性を取って知識を深めていきましょう。
もし、全く自分の興味の湧くことが分からなければ、この機会に「自分について」の棚卸をしてみましょう。
ちょっと自己啓発的な話になってしまいますが、己を知ることはビジネスにとっても非常に重要です。
なぜなら自分の事が分からなければ、相手の事も分からないからです。
心理学では自己認識のフレームワークに “ジョハリの窓” というのがあります。

自分が知らない領域「盲点の窓」「未知の窓」このあたりを深く考えてみましょう。
あんがい自分の事って自分でもよくわからないものです。
そして、落ち着いて自分自身について考える時間を持っている人は、そう多くありません。
日々の喧騒の中、目の前にあることを考えるのでいっぱいいっぱいになってしまうからです。
ぜひこの機会に、一度一人になって、静かな場所で “自分自身について” 考えてみてください。
思いの外、 自分のやりたいことや、興味のある分野に気づけるかもしれません・・・
③ 人がお金を払ってでも解決したい悩みとは
ビジネスで大きく稼げる領域は、 人がお金を払ってでも解決したい深い悩みがある場所です。
人の欲求には5段階の階層があり、それを示すフレームワークに「マズローの欲求5段階」 があります。

マズローの欲求5段階とは、 人間の欲求を5段階に分けてカテゴライズしたもので、 心理学者のアブラハム・マズローが提唱しているものになります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
第1段階:生理的欲求
生きるために必要最低限の欲求。
「食べること・寝ること」 など生命の維持に関わる欲求ですから絶対に満たす必要があります。
飲食店などは典型例です。
人が生きていく上で食べる事は必須ですから、顧客の欲求が強い分野ではあります。
その分ライバルも多く差別化が難しい側面もありますね。
枕とか寝具の物販ビジネスも需要は多いですがライバルが多い傾向です。
第2段階:安全欲求
安心して生活していくための欲求です。
雨風しのげる家があることや、不自由なく快適に生活したいと思う心理です。
例えばライフスタイルのジャンルや、 不動産関係、保険関係などのビジネスがここに該当します。
人はプロスペクト理論による損失回避の心理が非常に強い生き物です。
顧客は不安を解消するためであればお金を払ってでも解決したいと思うんですね。
第3段階:社会的欲求
コミュニティーへの欲求です。
人は何かに所属していると安心しますが、これは社会的欲求によるものです。
例えば、宗教もそうですし、ブランディングによる商品販売も実は社会的欲求の側面があります。
流行りのアイテムなんかは、持っているだけで “仲間の一員” のような気持ちになりますし、社会的欲求が満たされます。
会員制のビジネスなんかもそうですね。
オンラインサロンなどが分かりやすいでしょうか・・・所属の意識を満たせるわけですからね。
第4段階:承認欲求
認められたい・尊敬されたい・愛されたいと思う欲求です。
承認欲求には、他者からの承認を求める低次の欲求と、 自己承認の高次の欲求の2種類があります。
わかりやすい例でいくと恋愛系の領域のビジネスがここに当てはまります。
恋愛コンサルとか結婚相談所などは、「愛されたい」とか「認められたい」という気持ちを持ったユーザーが集まります。
第5段階:自己実現欲求
“自分” という人間を「もっと良くしよう」と思う欲求です。
自分の可能性への模索や、 自己研鑽がここに当たります。
資格の取得や学習型の領域はここに当てはまります。
例えば、オンラインスクールやコーチングなどのビジネスも自己実現欲求を満たすためのビジネスですよね。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
もっと具体的に解説しましょう!
以下の10個の根源的欲求に当てはまるビジネスは、大きく稼げる可能性があります!
※根源的欲求とはジェフリーラント博士によって提唱されている、人が最も本質的に行動する動機です。

④ 業界のプロである必要はない
個人で商品を作ろうと思った時、多くの方が不安に思うのはこういうことです。
「私はそんなに実績もないし上級者でもプロでもないのですが・・・」
結論から言って、自分の商品やサービスを持つのに業界のプロである必要はありません。
どのような場合でも、商品やサービスを購入する顧客というのは、初心者だったり・これから何かを始めようとしている段階の人がほとんどです。
もちろん中には「中級者〜上級者向け」の商品やサービスもあるかもしれませんが、そのパイは広くはありません。

このようにほとんどが決して上級者向けの悩みではないんですね。
「心理学を駆使した人心操作的話術」などの上級なコンテンツよりも、こういった基礎的なことの方が圧倒的に需要があります。
このレベルであれば、 例えばあなたが “10年間一緒のパートナーがいる” というだけでもサービス提供者になることができます。
- 出会うためにはどうしたらいいのか
- 関係を進展させるためにはどうしたらいいのか
- デートのポイント
- 付き合ってからの注意点
- 関係を継続するために大事なポイント
などなど話せることはいっぱいあるはずです。 
例えばあなたが「恋愛のプロフェッショナル」なら、そこから下の「恋愛のセミプロ」〜「恋愛未経験者」までがお客さんになります。もしあなたが「普通の恋愛経験者」なら、その下の「恋愛未経験者」はお客さんになりえます。
権威があればあるほど、幅広く顧客にリーチすることができますが、最上層でなくてもビジネスをすることができると覚えておきましょう。
⑤ 個人で販売できる商品の種類
ではどうやって、商品を形にしていけば良いのか?
ネットを使って個人で商品を販売する場合、種類は次のようなものがあります。

これらは大きく分けると無形商品と有形商品という形に分けられます。
note や Kindle など、テキストコンテンツを有料で販売するデジタルコンテンツ販売。
オンラインスクールやオンラインサロンなどのコミュニティ運営。
コンサルティングや相談サービスなどのオンラインサービス 。
オンラインセミナーなどでの指導。
Web ライティングや Web デザイン・動画編集などのスキル販売。
そして、オリジナルグッズや製品販売などの有形商品販売。
有形商品の製作は、簡単なオリジナルグッズの制作であれば初心者でもハードルが低く取り組むことができますが、製品販売は製作が必要になるので初心者にはハードルが高めです。
当講座では、基本的に無形商品の製作と販売を軸に学習を進めてまいります。

ネットを使って無形商品を販売するということは、1対Nで商品を提供できるということであり、高レバレッジなビジネスモデルです。有形商品と違い、あなたの知識や経験が商品になります。製作コストもかかりませんから、利益率は100%に近い形になります。
⑥ 販売方法
基本的にオンラインで販売します。
テキストコンテンツであれば、 PDF にまとめたり、そのようなプラットフォームを使うこともできます。
会員サイトを用意して当講座のように、テキスト×動画で提供することもできます。
相談サービスやコンサルティング・オンラインセミナーなどであればzoomやチャットワークを使ってサービスを提供します。細かい方法については、当講座のそれぞれのフェーズで掘り下げて学習していきましょう!
⑤マーケティングは計画が命
ここでは「マーケティングは計画が命」ということについてお話ししていきます。自分で商品を作って販売していくまでの流れは以下です。






その中でも特に①の 出来栄えによって、そのビジネスの未来が左右されると言っても過言ではありません。①は、 プロダクトを起点に考え、マーケティングの全体戦略を練る部分です。
マーケティングの全体戦略とは何か。






このように、これから商品を販売していく上で
- 誰に
- 何を
- どのように
売っていくのかしっかりと計画を立てます。言うなれば、ここは戦略の部分。
- ブログ運営
- YouTube
- SNS 運用
- Web ライティング
- SEO ライティング
- セールスライティング
- デザイン
こういう具体的な部分は “戦術の部分” です。
「どうやって戦っていくか?」戦略が決まってからで十分です。
どんなにSEOがわかっていても、どんなにフォロワーがいても、それをどう活かすのか?がわかってないと稼げません。
フォロワー数が多いのに稼げていない人って結構いますが、それは戦略をしっかり練らずに小手先のノウハウに翻弄されてるからです。
チャンネル登録者数やフォロワー数は、わかりやすい実績にはなりますが、それが “目的” ではありませんよね?
それは、ただ目的を達成するための手段にすぎません。
手段の目的化になってしまわないように、初期の段階でしっかりと戦略を練りましょう。
⑥顧客目線の重要性
マーケティングを行うとき、最も重要なのは顧客目線の考え方です。
それなのになぜか、商品を販売しようとするとき、私たちは自分よがりなマーケティングをしてしまいます。
大ベストセラー「人を動かす」の著者・デール・カーネギーは、こう言いました。

この意味がわかるでしょうか?
商売の基本は、価値の提供。
価値の提供とは顧客のニーズを満たすことであり、決してこちらの “売りたい気持ちを満たすこと” ではないということです。
ここで顧客目線についていくつか大事な話をしましょう。
①顧客自身も気づいていない悩みの解決

顧客は実は自分の悩みの多くに気づいていません。
自分で自覚している顕在ニーズは、いわば氷山の一角。
例えば、育毛剤を欲しい顧客にはどんなニーズがあるのでしょうか?

- 薄い髪の毛を何とかしたい
- 髪の毛をフサフサにしたい
- 抜け毛を予防したい
おそらくこれらのニーズは自分でも自覚しているはずです。
では続いて、それらのニーズに「なぜ?」を繰り返してみましょう!
なぜ?の問いかけーーーーーーーー
- 髪の毛を生やしたい→老けて見えるから
- 若返りたい→かっこよく見えるから
- かっこよくなりたい→モテたいから
- モテたい→ 愛されたい・認められたい(承認欲求)
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
このようになります。
つまり、顧客自身は気付いてないかもしれませんが、実は承認欲求を満たすための商品ニーズなんだということがわかります。
そこが分かると、コピーライティング・セールスライティングも訴求の切り口が違ってきます。
ドンピシャのメッセージを伝えることができれば商品の成約率(CVR)は、驚くほど高くなるものです。
②欲しいのは商品ではない
潜在的なニーズを考えるクセがつけば、顧客が欲しいものは商品やサービス自体ではないことに気付くはずです。
商品のその先にある本当のメリットのことを「ベネフィット」といいます。

例えばですが、鍋焼きうどんでおなじみの「株式会社キンレイ」は、あるとき冷凍うどんの販売を始めました。
「これは絶対売れるだろう」という期待と裏腹に商品は全く売れません。
そこでパッケージにあるコピーを追加したところ飛ぶように冷凍うどんは売れ始めました!
そのコピーがこちら。
「お水のいらない冷凍うどん」
そう。
顧客が冷凍うどんに求めていたものは、うどんそのものではなく「調理の手間を省くこと」だったのです。
これが、顧客のベネフィットに沿った訴求!
ベネフィットには2つの種類があります。

どちらも人がお金を払ってでも得たいベネフィットです。
そして覚えておいてほしいのが、どちらかというと人は “デメリットの回避” に強く反応します。

マメ知識・プロスペクト理論ーーーーーー
プロスペクト理論は、損失回避の心理をついた意思決定のメカニズムです。
人が行動する時は、なにかの価値を得たいからなのですが、それも2種類あります。
人間にとっての価値
- デメリットの回避
- メリットの獲得
そして、どちらの方が人を動かすかといえば損失(デメリット)の回避です。
プロスペクト理論の証明にこんなテストがあります。
- 100%の確率で4000円もらえるくじ
- 80%の確率で5000円をもらえるけど20%の確率で0円のくじ
どちらを選ぶか?といった実験です。
そして、大体の人が①の確実に4000円もらえる方のくじを選ぶんです。
得をしたいより、損したくない方が気持ち的に強いってことですね!
ーーーーーーーーーーーーーーーー
③私たちの仕事は気づきを与えること
顧客の目線にたった時、私たちのやるべきことは商品を売ることではありません。
もっともやるべきことは、気づきを与えること。
顧客自身も気づいていない潜在ニーズに気づかせ「どうか商品を売ってください!」といってもらえるようにすることです。そのためにはニーズとウォンツに気づかせなくてはいけません。

このように、ニーズだけを感じている状態では商品を買ってもらうことはできません。
商品に対するニーズに気づかせた上で、さらにベネフィットにも気づいてもらい顧客にウォンツを感じてもらう必要があります。
自分で商品を販売したい私たちマーケターのやることは、商品の機能説明でも購入してもらうための説得でもありません。
顧客との関係性がスタートし情報発信していく過程の中で、このニーズとウォンツに気づいてもらうべく教育していくことなんです。
これをマーケティング用語で「ナーチャリング」と言います。
顧客の購買心理をしっかりと醸成することで、クレームやトラブルを最小限に抑えることができます。
⑦「良い商品は売れる」は嘘
ここでは「良い商品は売れる」と思っている人に向けて、真実をお話ししていきます。
残念ながら「商品が良ければ売れる」というのは全くの勘違いです。
語弊を恐れずに言うのであれば、 このネットの世界では「どうであるか?」より「どう見えるか?」 の方が重要だったりします。
つまり、見せ方が全てであり、伝え方が命であるという話です。
ただし当講座で、私が指導する内容としては「ゴミみたいな商品をピカピカに磨いたマーケティングで売りまくれ!」という話ではありません。
そこだけは注意して欲しいと思います。
“良い商品である” というのは大大大前提だと思って学習を進めてください。
① 伝え方が命
「一度使ってさえもらえば、この商品の良さわかってもらえるんだけどな〜・・・」
売れないマーケターほどこう言います。
いくら商品がよくても伝わらなければ、ないのも一緒なんですよ。
人がお金を払ってでも行動する根源的欲求を覚えているだろうか?
これらの欲求をくすぐるような印象を与えなければ、人は動きません。
特に、無形商品であるデジタルコンテンツなんかは、買ってみないと中身がわかりませんし、
味見するわけにもいきませんしね・・・
そんな時、人はどこで商品の良し悪しを判断するのか?
それこそが “印象” であり、その印象をどう伝えるのか?がマーケティングでもあります。
根源的欲求をくすぐるような伝え方をするには何が必要か?
それは、言語化能力とライティング力です。
デジタルコンテンツの最終的な購入の決定はLP(販売ページ)で成されます。
売上はLPの出来栄え次第といってもいい!!
それぐらいウェイトの大きい部分です。
そのLPで、商品のベネフィットをいかに顧客に想起させられるか?
それが、概念を言語化する能力だったり、文章として表現するライティング力だったりするわけです。
そうでなくては、“いい商品” は相手にそう伝わりません。
当講座では、売上の全てを握るともいえるLPの書き方についても深く学習していきます。
② 伝え方の事例
「伝え方が大事」と言われても、具体的にイメージができないと意味がありません。
ここでいくつかマーケティングの中で伝え方がいかに大事かわかる事例を紹介します。
これからお話しする事例は全て、商品(中身)の本質は変えていないのに、伝え方を変えただけで反応が大きく変わったお話しです。
2-1 ホームレスの物乞いのメッセージ

とあるホームレスは、道端で物乞いをしていました。
彼は、盲目でした。
道ゆく人たちにお金を恵んでもらえるように、寒い路上を何時間も座って待っています。
ダンボールには、こう書かれていました。
「私は盲目です。お金を恵んでください」と。
なんともストレートなメッセージです。
しかし、何時間まってもお金を投げ入れてくれる人はいません・・・
そこに、ある女性が近寄ってきました。
彼女は、彼の側にいくと、メッセージが書いてあるダンボールに、なにやら書いてるようでした。
しかし、盲目の彼にはわかりません。
「イラズラでもされたかな・・・?」
そう思った途端、道ゆく人たちがどんどんお金を投げ入れてくれるではありませんか!?
そう。実は彼女はダンボールに書かれたメッセージを書き換えていたのでした。
「今日はとても素晴らしい日!!でも私にはそれが見えない・・・」と。
2-1 MacBookのプレゼン

これは有名な話ですが、Appleの創設者・スティーブジョブズが MacBook Air を発表したときの話です。
当時のノートパソコンといえば、分厚くてゴツゴツしててとてもスタリッシュではなかったんですね。
そこで彼は MacBookAir の良さを伝えるやり方にこだわりました。
彼はなんと大衆の前で MacBook Air を紙袋から取り出して見せたんです!
「軽くて・薄くて・スタイリッシュ」
そんな言葉を使わなくても、それは伝わりました。
そんなスティーブジョブズはこうも言っています。
「いくら素晴らしいものをつくっても、伝えなければ、ないのと同じ」と。
2-3 冷凍うどんのパッケージ
鍋焼きうどんでお馴染みの株式会社キンレイは、冷凍うどんを発売したが、全く売れずに困っていた。
通常はアルミ鍋で加熱して食べる家庭用のうどんだったのだが、冷凍にすることで手軽に食べられる。
てっきり売れるものだと思っていたのだ。
しかし、店頭に並べるもほとんど売れず、一時は撤退も考えたそうだ。
そんな冷凍うどんが劇的に売れたのは、パッケージにある言葉を加えたからだ。
「お水のいらない冷凍うどん」
そう。顧客が求めていたのは、うどんそのものではなく「作る手間を省くこと」だったのだ。
2-4 スーパーのトイレの張り紙

トイレの個室の中には、決まって張り紙が貼ってあったりします。
なるべくキレイに使ってほしいですから「トイレはキレイに使いましょう」と書きますよね?
ですが、それでは一向にキレイになりませんでした。
むしろお客さんの中には「トイレにいってまで命令されてるようで不快だ」と言った人までいたそうです。
そこで張り紙に書いてある文章をこう変えました。
「いつもキレイにご利用いただきありがとうございます!」と。
このメッセージに変えてから、効果は抜群なのだとか・・・
これは「感謝されたい」という人の欲をうまく突いたメッセージですよね。
2-5 売れなかったカップヌードル

みんな誰もが知ってるカップヌードル。
日本では定番商品なんですが、アメリカで発売したときには全く売れなかったそうです。
その頃のアメリカではカップ麺というジャンルが確立されておらず、受け入れられなかった。
営業マンが何度スーパーにお願いするも、置いてもらうことすらできず途方にくれていたのだ。
そこで、伝え方を変えた。
「これは具だくさんのスープです!」
スープであれば、アメリカ人にも馴染み深く、あっさりと受け入れられたのだ。
今では、世界累計販売数は400億食を超えている。
③ 伝え方の事例の考察
これらの事例は、全て伝え方のみを変えたお話しでしたね。
中身は関係なく。
では、どんな風に伝えたのか?
それこそがベネフィットに訴えかけたメッセージです。
これですね。

今の時代「良い商品である」のは、当然なのです。
問題は、相手にどんな印象で伝わるのか?
どんなベネフィットを伝えられるか?
これを忘れてはいけません。
スティーブ・ジョブズの言葉を、ここでもう一度お借りします。
「いくら素晴らしいものをつくっても、伝えなければ、ないのと同じ」
⑧態度変容モデル
ここでは態度変容モデルについて学習していきます。

顧客は、商品やサービスを知ったからといって、いきなり「買いたい!」とは、なりません。
そこに行き着くまでの道のりの中で、消費者はある程度決まった行動をとると言われています。
そして、その顧客の行動と心の流れに合わせたアクションが販売者側にも必要になるんですね。
購買に至るまでの道のりで、顧客の購買意欲を醸成していく過程こそマーケティングの醍醐味であり、腕前のみせどころだと言えます。
このような顧客の行動と心理の流れをカスタマージャーニーともいったりしますね。

①一般的な態度変容モデル「AIDMA 」
こちらが一般的な顧客の購買心理の流れを表した態度変容モデル「AIDMA」です。
1-1 ATTENTION
まず、どんなビジネスでも初めは認知されることから始まります。
自分のお客様となり得るペルソナに自分の存在を認知してもらわないことには、何も始まりません。
認知を拡大するためには情報発信することが必要です。
認知拡大の3つの方法ーーーー
- 検索結果で知ってもらう
- SNS で知ってもらう
- 広告で知ってもらう
ーーーーーーーーーーーーーー
このような形で自分のコンテンツの露出を増やし、自分の存在に気づいてもらわなくてはいけません。
1-2 INTEREST
前段階で顧客にあなたの存在を知ってもらったとしても、 それだけでは売上には繋がりません。
「ふーん・・・こんな人いるんだ」これぐらいの温度感です。
そこからさらに関係性を深めていくためには、あなたに興味を持ってもらわなくてはいけません。
では、どうすれば興味を持ってもらえるのでしょうか?
それは、顧客があなたのコンテンツに価値を感じた時です。
では、どんなコンテンツであれば価値を感じるのか?
それは、自分の悩みを解決してくれるような有益なコンテンツだった時です。
- 「ん? これちょうど知りたかったことだ!」
- 「うわー詳しくかいてあるなー・・・わかりやす!」
- 「ていうか、この人誰?」
こうなると顧客はあなたの情報をその都度追うようになります。
1-3 DESIRE
あなたの情報を常に追っていると、何やら商品を持っていることがわかりました。
興味のある人物が販売している商品なので、気にはなるのだけど、必要性も分からなければ「買おう」とも思っていない段階です。
私たちにも経験がありますよね?
「よく見かけるインフルエンサーが、何やら商品を販売するらしい・・・」
こんな情報を聞きつけて「へー・・・ どんな商品なんだろう?」と思うことはあっても、次の日には忘れてしまう。
こんな具合です。
ここで私達がしなくてはいけないのは2つ。
- 商品の “必要性を感じてもらう” コンテンツを見てもらうこと(ニーズ教育)
- 商品を “欲しいと思ってもらう” コンテンツを見てもらうこと(ウォンツ教育)
1-4 MEMORY
残念ながら商品に興味を持って「欲しい!」と思っても、 その回数が少なければ人は簡単に忘れてしまいます。
欲しかったけど買うのを忘れて結局買わなかった商品・・・ ありますよね?
実は、顧客に良い印象を与えることより、よっぽど忘れられないことの方が大切なんです。
忘れられてしまったら、ATTENTION(認知)からやり直しですからね!
そこで記憶にしっかり定着させるために、こまめな情報発信をしていきます。
自分や自分の商品に関しての情報が何度も顧客の目に入るようにしなくてはいけません。
そうすると、単純接触効果(ザイオンス効果)が発揮され、商品やサービスにも親近感が湧いてきますし、より欲しい気持ちが成熟してきます。
1-5 ACTION
ここにきてようやく商品を購入しようかどうかあと一歩のところです。
ですが、顧客は損失回避の心理を強く持っていますから、不安が払拭されない限り商品を購入はしません。
- 価格
- 使いやすさ
- 評判
- トラブルの対応
どんな商品でも購入する前にこの辺りのことが気になるんです。
このような不安を販売ページ(LP)でしっかり解消して、購入までの一歩を後押ししてあげましょう。
商品の購入がスムーズに進むような導線も大切です。
申し込みフォームが分かりづらかったり、手間がかかったりすると「やっぱり今度でいいや」となって二度と購入してくれなくなります。
②ネット時代の態度変容モデル「AISAS」

インターネットが発達した現代の態度変容モデルが「AISAS」です。
今の時代は何でもインターネットを使って完結しますから、消費行動も一昔前とは変わってきました。
一般的な態度変容モデル「AIDMA」の 第1段階「ATTENTION」と第2段階 「INTEREST」までは同じです。
やはり、認知拡大をしてから、情報発信による価値提供で興味を持ってもらうのは必須ですからね。
特徴的なのはその後の第3段階からです。
2-1 SEACH
インターネットでの消費行動の最も王道な方法として「検索する」があります。
興味を持った人物やサービスのことを Google で検索したことありますよね?
その人のブログの内容やサービスの内容までもっと詳しく知りたいときは、“検索” するわけです。
ここで他の人と変わらないような情報を発信していたり、サービス内容が普通のものと代わり映えしないようなものであれば、そこで終わってしまいます。
だからこそ検索したユーザーに見てもらうコンテンツは、他とは違った価値を提供していなくてはいけません。
ブランディングや自分だけの世界観で、圧倒的に差別化された価値を提供しましょう。
2-2 ACTION
最近では「何を買うか?」ではなく「誰から買うか?」 が重要になってきています。
前段階の時点でしっかりとブランディングされた価値を提供できていた場合、購入へのハードルはそんなに高いものではありません。
一般的な態度変容モデルの AIDMAと同様、 販売ページ(LP)でしっかり不安を払拭しスムーズに購入できるようにしましょう。
2-3 SHERE
そして、最も特徴的なのがこの段階。
現代の消費行動の最終段階は「SHERE」です。
昔はマーケティングの方向性は一方向にしかありませんでした。
企業が商品を開発し、 CM を打って認知拡大を図り、興味を持った消費者が商品を購入する。
その繰り返しでした。
しかしながら現代のマーケティングの主役は、販売者ではなく “消費者” の方なんです。
良い商品を購入した消費者は、レビューを買いたりSNSで拡散したり、友達に LINE で教えたりします。
その情報を目にした別のユーザーはさらに検索し商品を購入しまたSHEREする・・・それがスパイラルのようにぐるぐる回る感じ。
一方向ではなく円のように循環する形となりました。
「顧客が顧客を呼んでくる」そんなイメージです。
ここで良い口コミを発生させるためには、 良い商品であることは大前提のもとで、口コミを発生させるための仕掛けが必要です。
例えば
「素敵な口コミを投稿してくれた方の中から〇〇名様に、 Amazon ギフト券プレゼント!」などです。
どんなものでもいいのですが、ポジティブな口コミはこちらから声かけしない限り能動的に発生するものではありません。
※ネガティブな口コミは能動的な理由(クレーム)があるので顧客は自発的に書きます。
③SNS時代の態度変容モデル「ALTAS」

最も新しい態度変容モデルが「ALTAS(アルタス)」です。
インターネットが発達した現代の中で最も新しい文化は SNS です。
現在の検索行動は、 Google や Yahoo などのブラウザ検索のみで行われるものではなくなってきています。
「ググる」にプラスして、「タグる」といったSNS検索も同時に使う若者が増えてきています。

引用元:博報堂
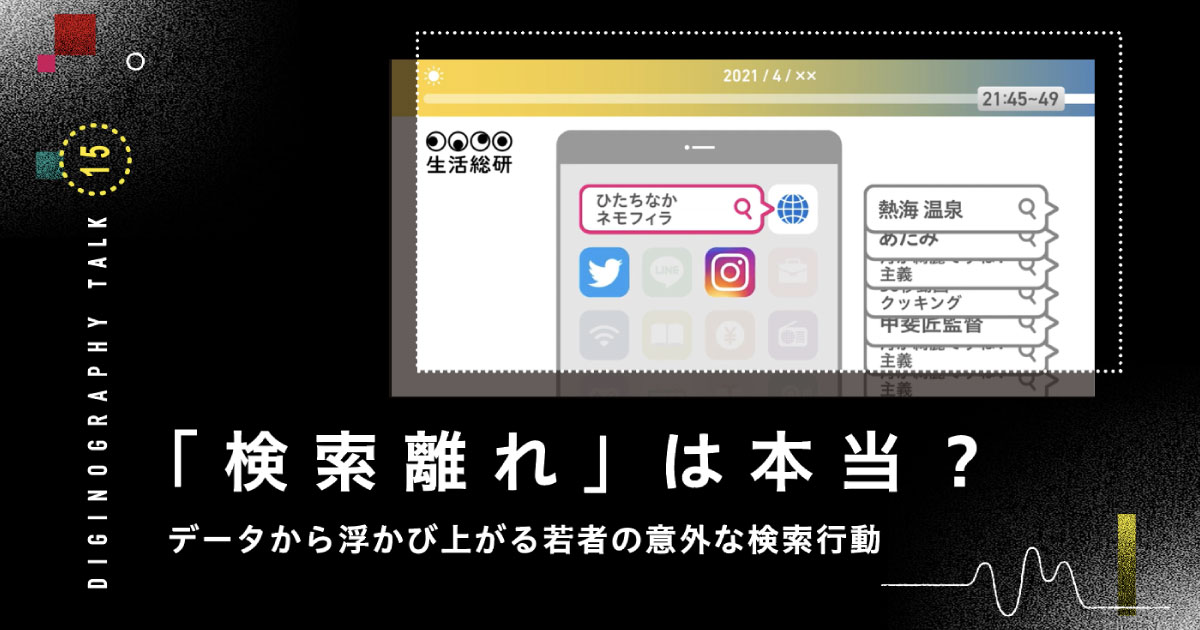
このようなSNS時代の消費者行動には、ブラウザ検索だけで考えられていた「AISAS」とも違った行動パターンがあります。基本的にATTENTION(認知)とACTION(行動)とSHERE(拡散)は、AISASの法則と一緒です。
特徴的なのは「LIKE」と「TRUST」。
3-1 LIKE
どこかでその人の情報を知ったら、今はまずその人の SNS アカウントを見に行きます。
そして、投稿にいいねしたり、フォローしたり、チャンネル登録したりするわけです。
自分のビジネスのターゲットであるペルソナが、好むような情報発信ができていれば、エンゲージメント(いいねとかリツイートなどの反応)を得ることができますよね。
SNS 時代に最も大切なのはその人の世界観だったりブランディングです。
- 自分の好きなインフルエンサーが使っている化粧品だから買った
- いつも見ているYouTuberが新しいサービスを出したから登録した
人々はこういった感覚で商品を購入するようになってきています。
「いかに顧客が好むような世界観を演出できるか?」
この言葉は非常に抽象的ですが、今の時代において最も重要なことでもあります。
3-2 TRUST
「誰から買うか」が最も購買の決定要因として強くなってきた昨今、販売者と消費者の信頼関係の深さは売上にダイレクトに現れます。
顧客から信頼されないと物は売れません。
顧客との関係を深めていくためには、 圧倒的な価値の提供とコミュニケーションが欠かせません。
“価値の提供” とは、普段の情報発信の質だと考えてください。
- どれぐらい顧客目線になれているか
- 顧客の気持ちを分かっているか
- 顧客の欲しいものを提供できているか
- ライバルより圧倒的にクオリティが高いか
この辺りです。
今はみんな情報発信の質が高いのが常識です。
その常識の中で、いかに異常値を叩き出せるか?ここを真剣に考えてください。
他の人ができることを、他の人と同じ程度できるだけでは顧客に価値を感じてもらうことはできませんからね。
これをスムーズに行えるのが、 LINE やメルマガなどのクローズドな場所です。
コミュニケーションをとりつつ、顧客に寄り添った情報発信ができるため、顧客との距離が非常に近くなり一気にファン化します。
④どれを使えばいいのか?
ここまで三つの態度変容モデルを紹介しましたが「いったいどれを使えばいいんだ?」こう思った方もいるのではないでしょうか?
結論としては、どれを使っても構いません。
大まかな流れだけ頭の片隅においておいてください。
モノが売れる仕組みと、その流れには、どのようなモデルであったとしても、
【認知から始まり、 情報発信しながら集客し、販売する】
これが基本なのです。
インターネットという特性をプラスすることによって、最終的にエンドユーザーのシェアという行動が加わっただけです。
基本的には、認知〜販売までが最もコアな部分であることは変わりません。
そして、実はこの講座の学習の流れも、態度変容モデルに則って組み立てられています。
順番に学習し理解して実行することで、 顧客の購買心理に寄り添ったマーケティングを行うことができます。

コメント